1-1. ChatGPTの共有機能とは?仕組みを3行で理解
「ChatGPTとの会話を、他の人と簡単にシェアできたらいいのに…」そう思ったことはありませんか?
実は、その願いを叶えるのが 「共有リンク」機能 です。
- 会話をリンク化して他人に渡せる
- 相手はインポートして続きを進められる
- 元の会話は上書きされない
これが仕組みの全体像です。
たとえば、
あなたがChatGPTに依頼して「事業計画の叩き台」を作ったとします。
その結果を仲間に見てもらいたいとき、ファイルに書き写す必要はありません。
リンク1つを送れば、相手はすぐに同じ会話を見られるのです。
「もし相手が続きを質問したら、自分の会話が書き換わってしまうのでは?」
と不安になりますよね。
安心してください。相手側は自分の履歴にコピーして続きを行うので、あなたの元の会話はそのまま残ります。
つまり
「オリジナルを守りつつ、人に続きを任せられる」
仕組みになっているのです。
1-2. 本記事で解決できること

「どうやって共有するのか?」
「相手にはどう見えるのか?」
「実際にどんな便利な活用ができるのか?」
この記事では、その疑問に順番に答えていきます。
さらに、共有機能を利用した、革新的な活用法5選 も紹介します。
最後まで読めば、共有リンクを単なる“会話のコピー”ではなく、チームを動かす武器として活用できるようになるはずです。
📚 出典: OpenAI Help Center – Share chats in ChatGPT
2-1. ChatGPT 共有リンクの作り方(PC/モバイル共通)
「共有リンクって、どこから作るの?」と最初に迷う人は多いです。
実際の手順はとてもシンプルです。
1.ChatGPTで共有したい会話を開きます。
2.右上の「…(その他メニュー)」をクリック。(スマートフォンの場合)
3.「共有」ボタンを選び、リンクを生成。(PCの場合はデフォルトで表示されています)


4.出てきたURLをコピーして、メールやチャットに貼り付け。

これだけです。
PCでもスマホアプリでも大きな流れは同じですが、アイコンの位置やデザインが少し違います。
「ボタンが見つからない」と思ったら、まず右上のメニューを探してください。
2-2. 相手側の見え方と挙動
さて、そのリンクを受け取った相手はどう見えるのでしょうか?
↓リンクを開くと、会話の全体が表示されます。
ChatGPTのアカウントを持たないユーザーでも確認できます。

相手は途中からやり取りを開始できます。

ここで大切なのは、あなたの元の会話は影響を受けないということです。
つまり、相手が会話を大きく書き換えても、あなたの履歴は一切変わりません。
基礎となる情報や前提条件はそのままに、思考の分岐ができるのがすごい・・・!!!
「共有リンクを削除したら、相手のコピーも消えるの?」
残念ながら、ほかのユーザーに一度インポートされた内容は消せません。(要注意)
ただし、リンクそのものは削除できるので「これ以上は他の人に見せたくない」という状況には対応可能です。
2-3. できること・できないこと一覧
ここで一度、できることとできないことを整理しましょう。
できること
リンクを作って他人に見せる
相手がインポートして続きから質問する
あなたも会話を更新してOK
(共有リンクはリアルタイム更新ではなく“その時点のコピー”)
できないこと
相手と「同じ画面」で同時編集する(共同編集は不可)
一度インポートされてしまった相手の履歴を削除する
「共同編集」ではなく「複製して各自で進める」というのが、この機能の基本です。
3-1. ChatGPT共有機能の革新的活用法5選
共有リンクは「会話を見せるだけの仕組み」ではありません。
工夫次第で、チームの働き方や学習の仕組みを大きく変える武器になります。
ここでは、初心者でもすぐ試せる5つの活用法を紹介します。
活用法その1:方向性→具体化のバトンリレー

「大枠の方向性は決まったけど、細かいことまでは自分で考えたくない」
そんなときに役立つのがバトンリレー型の共有です。
たとえばイベント企画の場合。
あなたがChatGPTと一緒に「イベントのコンセプト」や「全体の流れ」を決めたとします。
コンセプト:地域の親子向けアクティビティ体験イベント
最終ゴール:地域への愛着形成→参加者に「また来たい」「地域に住んでよかった」と思ってもらう。
流れ:オープニング・体験コーナー・トークイベント・クロージング
ここまではあなたが決めておきます。
しかし
「具体的にどんな体験コーナーを入れる?」「トークイベントのテーマは?」
という細部は、チームメンバーに考えてほしい。
このとき、会話を共有リンクにして渡すと、メンバーは続きから、こう指示できます。
「体験コーナーの候補を5つ出して。低予算でできるアイデアに絞って」
「トークイベントのテーマを3つ提案して。それぞれ登壇者の候補も出して」
結果として、あなたは“大枠”を決める役割に集中し、メンバーは“具体化”に専念できます。
これは、まさに駅伝のタスキを渡すように、会話を次の走者にバトンリレーするイメージです。
手順
- ChatGPTに「イベントの目的・対象・全体の流れ」を入力
- GPTがまとめた戦略的アウトラインを保存
- 会話を共有リンク化し、チームに送る
- メンバーはインポートして「具体的な施策を提案して」と続きを依頼
活用法その2. リアルタイムQAハブ

「マニュアルはあるけど、読むのが面倒くさい」
「FAQを探すより、直接聞けたら早いのに」
そんなときに役立つのが リアルタイムQAハブ型の共有 です。
たとえば社内の経費精算ルール。
あなたがChatGPTに
「経費精算のよくある質問を整理して」
と依頼すると、
交通費の上限・領収書の要不要・提出期限といった項目をまとめてくれます。
追加で、社内のルールファイルをGPTに読みこませておいた上で、
この会話を共有リンクにして、SlackのチャンネルやNotionのFAQページに貼っておきます。
すると、社員はそのリンクを開き、続きからこう質問できます。
「タクシー代は深夜ならOK?」
「領収書をなくした場合はどうすればいい?」
ChatGPTがすぐに答えてくれるので、静的なPDFマニュアルを読むよりも直感的です。
まさに“動くマニュアル”が1本のリンクで実現します。
→このあたり、NoteBook LMというものを使うとさらに便利になるのですが、それはまた別の記事で紹介したいと思います!
手順
- ChatGPTに「よくある質問と回答」を入力して整理
- 会話を共有リンク化
- SlackやNotionなど社内ツールにリンクを常設
- メンバーはリンクを開いて、疑問を続きから質問
結果として、情報共有の手間が減り、社員は「わからない」を即時に解消できます。
問い合わせ担当者の負担も軽くなり、社内全体の効率が上がります。
3. 成果物に対する多角的レビュー

「資料のレビュー、毎回メールで回していたら時間がかかる」
「AIと会話しても視点が広がらない」
そんなときに役立つのが 多角的レビュー回収型の共有 です。
たとえば提案書のドラフト。あなたが、
ChatGPTに提案書の要点をまとめてもらった会話を共有リンクにして、チームに渡します。
するとメンバーはそのリンクを開き、各々の視点からこう指示できます。
「このロジックに抜けはない?」
「説得力を高めるための具体例はあるか?」
それぞれが自分の履歴にインポートしてレビューできるので、同じベースから改善案が集まります。
また、こちらも相手の思考回路が相手とGPTの会話からわかるため超便利です。
手順
- ChatGPTに提案書や記事を要約させる
- 会話を共有リンク化
- レビュー依頼と一緒にチームへ送る
- メンバーはインポートして「改善点を出して」とGPTに質問
4. 教育・トレーニング教材化

「文章やプロンプトの“お手本”を見ながら練習できたらいいのに」
そんなときに役立つのが 教材化型の共有 です
たとえば、非IT部門にChatGPTの使い方を教えるシーン。
あなたがChatGPTに
「商品説明をわかりやすく書き直す」プロンプトを入力し、模範的な会話を作ります。
それを共有リンクにして渡す。
そうすると受講者は模範的なプロンプトがどういったものなのか、回答は普段のGPTとはどれくらい違うのか。
身をもって体験・確認できます。
「同じ説明文を、今度は“中学生向け”に書き直して」
「SNS投稿用に短くして」
こうして受講者は、ただ読むだけでなく実際に手を動かして学べるのです。
静的な教材よりも圧倒的に実践的で、理解も定着も早くなります。
手順
- ChatGPTと模範的な会話(例:良いプロンプトと回答)を行う
- その会話を共有リンク化
- 学習者に配布してインポートさせる
- 学習者は続きから自分なりに質問・改善を試す
結果として、教材が「読むもの」から「使って体験するもの」へ進化します。
新人研修や社内勉強会での効果は抜群です。
5. コンペティション型活用

「同じテーマに対してみんなが取り組んだら、誰のアウトプットが一番いいだろう?」
そんな遊び心を仕事や学習に持ち込めるのが コンペティション型の共有 です。
たとえば新商品のキャッチコピーを考えるとします。
活用法その1を参考にして前提条件とゴールまで固めたChatGPTとの対話を参加者に配布します。
各メンバーがChatGPTに相談しながら、自分なりのコピーを作ります。
できあがった会話を共有リンク化し、全員で持ち寄ります。
リンクを開けば「どういうやり取りを経て、そのコピーにたどり着いたのか」も見えるので、単なる結果比較ではなくプロセス比較もできます。
そのうえで、みんなで投票したりディスカッションしたりすれば、楽しみながらスキルアップが可能です。
教育の場面でも同じです。
「このテーマで説明文を書いて」と学生に課題を出し、各自がChatGPTとの会話を提出。
先生や仲間が共有リンクを見比べて「どの説明が一番わかりやすいか」を話し合うと、自然に学び合いの場が生まれます。
手順
- テーマ(例:キャッチコピー・説明文・アイデア出し)を決める
- 各メンバーがChatGPTと会話してアウトプットを作成
- 会話を共有リンク化して提出・持ち寄る
- 全員で比較・投票・ディスカッション
効果→(これは実際行ったことがあり、参加者からの感想です!)
- チームでは「ゲーミフィケーション」で士気が上がる
- 教育現場では「他人の思考プロセスから学ぶ」機会が得られる
- 単なる成果物比較ではなく、思考の深さや工夫を可視化できる
まとめ
今回の記事では、ChatGPTの共有リンクを「ただ会話を見せる仕組み」ではなく、
戦略→施策のバトンリレー / リアルタイムQAハブ / 成果物レビュー / 教材化 / コンペティション型活用
の5つの切り口で紹介しました。
要点をひとことでまとめると、共有リンクは“人とAIをつなぐ架け橋”になり、チームの生産性を何倍にも高められるということです。
今日から実践できるOne Thing
👉 まずは「自分の過去の会話」を1つだけ共有リンクにして、同僚や友人に送ってみてください。
実行ステップ(15分以内)
- ChatGPTの履歴から1つ会話を選ぶ
- 右上メニューの「共有」からリンクをコピー
- チャットやメールで気軽にシェア
たったこれだけで、「なるほど!こう見えるんだ」と実感できます。
ひとこと
私自身も最初は「共有なんて必要かな?」と思っていました。
でも、提案資料の下書きを仲間にリンクで渡したとき、“一瞬でアイデアが返ってくるスピード感”に驚きました。
あの体験があったから、いまは特に企画段階での業務に欠かせない機能になっています。
読者へのメッセージ
ここまで読んでくださったあなたなら、きっと共有リンクを使いこなせるはずです。
もっとリアルな体験談や最新の活用法は、私の X(旧Twitter) で発信しています。
👉 気軽にフォローしていただけると嬉しいです。

また、「この記事を読んで実践してみた」「こんな場面で役立った」などの感想も、ぜひコメントで教えてください。
皆様の声が、次の記事を書く大きなヒントになります。
次回予告
次回は 「ChatGPT共有をチーム全体で運用するベストプラクティス」 を解説予定です。
記事の更新日は【2025年9月20日】。ぜひまた読みに来てください。




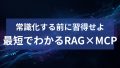
コメント